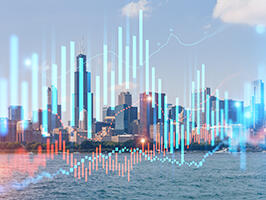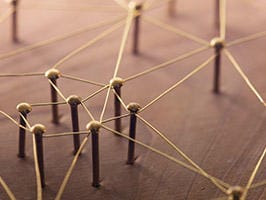Legacy from 2020
“レガシー(Legacy)”と聞いて何を思い浮かべるだろうか。某自動車メーカーのブランドが一番多いように思われるが、IT業界や金融業界では、古いシステム(レガシーデバイス)や金融危機以降の不良債権(レガシーローン)などを指すことがあり、必ずしも良い意味で使われるわけではない。ただし、本来は「遺産」という意味が一般的で、先祖や過去から受け継ぐものとして活用されることが多い。
最近、このレガシーという言葉が、あるイベントで多く見られる。2020年の東京オリンピックである。なお、レガシーという言葉自体は、今回の東京オリンピックに限ったものではなく、国際オリンピック委員会(IOC)においては以前からアピールされているキーワードで、大会開催に伴って整備した施設などを無駄にすることなく、後世まで活用することを意図して利用されている。具体的には、IOCが2013年に発表した『Olympic Legacy Booklet』に次の5つが示されている。
1.Sporting Legacy(スポーツレガシー):競技施設の整備、スポーツ振興など
2.Social Legacies(社会レガシー):文化や歴史などの理解向上、協働体制の構築など
3.Environmental Legacies(環境レガシー):都市環境の再生、新エネルギーの活用など
4.Urban Legacies(都市レガシー):都市開発、輸送インフラの整備など
5.Economic Legacies(経済レガシー):経済成長への寄与
ハードからソフトまで、さまざまなレガシーに言及しているが、やはり気になるのが、施設やインフラ整備などハード面のレガシーである。特にスポーツ施設に関しては、国が主体となる「新国立競技場」を始め、東京都による「海の森水上競技場(ボート、カヌー競技場)」など多額の支出を伴う施設がめじろ押しとなっている。整備総額が気になる部分ではあるが、今回はあくまでレガシーとしての後利用、すなわち、維持管理・運営などについて考えてみたい。もちろん、国や東京都としても、新たに整備される施設の今後について、検討を進めている。国は、新国立競技場に関して、大会後に民間運営への移行を図ることとしており、2015年12月に「大会後の運営管理に関する検討ワーキングチーム」(以下、「WT」)をスポーツ庁に設置した。また東京都では、2014年12月から「新規恒久施設等の後利用に関するアドバイザリー会議」(以下、「アドバイザリー会議」)が複数回開催され、2015年6月にその方向性が示されている。ただし、先行している東京都においても、具体的な施策はこれからで、国のWTについてはまだ端緒というイメージである。
ひとえにスポーツ施設といっても、維持管理・運営の手間はかなりのもので、例えば国のWT(2016年2月10日会合)で公開された資料では、国内の代表的な競技場として2002年のFIFA(国際サッカー連盟)ワールドカップで使用された10競技場の収支(2014年度)が示されているが、自治体からの指定管理料なしで黒字運営がなされているのは1競技場(札幌ドーム)のみである。サッカー競技場運営の難しさ(天然芝の管理など)もあるが、競技場運営全般の厳しさがうかがい知れる。見方を変えれば、後利用に関して、維持管理・運営ノウハウが非常に重要ということになる。
費用面での負担も大きく、開・閉会式含めて、さまざまな競技が実施される予定の新国立競技場の維持管理費については、事業主体である独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)が公開している民間共同事業体(大成建設・梓設計・隈研吾建築都市設計事務所)の技術提案書によれば、建設費約1,490億円に対して、別途、約1,000億円(50年間(税抜))が想定されている。しかし、実際の維持管理業務を当該共同事業体に任せるわけではないため、数字は保証されているものではない。JSCによる当初計画案で示された維持管理費は約2,798億円(50年間)となっており、どの程度当初想定費用から負担が低減されるかは、今後選定されるであろう維持管理・運営を担う事業者次第ということになる。
なお、東京都においては、各施設が目的別(開催種目別)に区分されていることもあり、後利用についても、各種目のアジア・世界選手権などの開催や施設の利用者層を想定した整理がなされている。ただし、こちらも維持管理・運営に関しては、指定管理者方式の活用などが一部提示されているものの、具体的な事業者などが存在するわけではなく、財政負担も含め、今後の課題として残る部分である。
以上のように、国、東京都とも、素晴らしい施設整備を進めながら、現時点では、新国立競技場においては設計・施工までの事業者選定、東京都においても代表的な施設について、設計・施工一括(デザインビルド)方式の採用となっており、維持管理・運営に関する計画は切り離されて検討が進んでいる。これに関しては、大会開催前の早い段階で、維持管理・運営についても、より具体的な方向性を示していくことが、魅力的なレガシーとして存在していくための重要なポイントになろう。
最後に、先例に倣うという意味で、JSCや東京都のアドバイザリー会議などでも一部取り上げられた、2012年のロンドンオリンピックにおける取組みを見てみたい。ロンドンオリンピックでは、競技場の後利用や大会後の周辺地域整備を担う組織として、ロンドンレガシー開発公社(London Legacy Development Corporation(以下、「LLDC」))という事業主体が設立されている。LLDCは、メイン会場であったオリンピックスタジアムにサッカープレミアリーグのチーム(West Ham United FC)を主要テナントとして誘致したり、ファシリティマネジメント関連事業で実績のあるCofely社を、継続活用されるオリンピックパークの施設管理・エネルギー供給事業者に選定するなどの事業を展開している。LLDCはオリンピック開催年の2012年に設立されているが、それ以前の2009年から、後利用を専門に扱う組織として運営されていたオリンピックパークレガシー公社(Olympic Park Legacy Company)の後継組織として位置づけられたものであり、大会開催前から、施設の維持管理・運営まで配慮した事業展開がなされてきたと言える。
ロンドンもしかり、東京のような一定程度成熟した都市でも、オリンピック開催に際しては、多額の事業費がかかるのは言うまでもない。残されるインフラやスポーツ施設などについては、財政負担のみが先行する“負の遺産”とならぬよう、国や東京都、民間事業者などが一体となって、後世まで活用される“オリンピックレガシー”を目指していかなければならない。そのために、開催前の準備期間から、維持管理・運営事業までの一貫した体制構築について、より活発的な議論がなされることを期待したい。
関連する分野・テーマをもっと読む