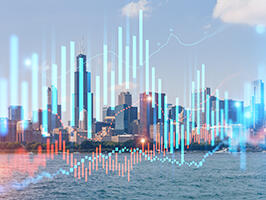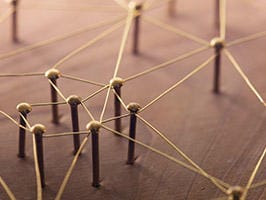森林ファンド元年(下) -山を動かす-
前稿では北米を中心に、機関投資家による森林ファンドへの投資が確立されているということを述べた。では、日本の森林には、その可能性はあるだろうか?
日本の林業や木材関連産業を語るとき、「日本の面積の約7割は森林であり、戦後植林された人工林は樹齢50年~60年を迎え成熟期にあるが、木材価格の低迷により林業は長期的に低迷している」ということが枕詞として使われる。さらに、「日本の森林は急峻な地形が多く、森林所有も零細規模が大多数であり、生産効率が悪い」とか、「人口減少により木材需要の増加は期待ができない」といったことばが続くことも定番である。このような環境下で、森林ファンドは、実現可能なのか?もし日本で森林ファンドが成立するとすれば、その必要条件は何なのか?
こうした問題意識のもとに、筆者らは2015年10月に「森林ファンド研究会」を立ち上げ、公益財団法人トラスト未来フォーラムの研究助成を受け、月例研究会を重ねた。研究会としての結論に筆者の考えを付加すると、森林ファンドの成立条件は、①インフラ整備(情報インフラ、林道整備)、②収益性の向上、③相当程度まとまった規模の森林、④金融・投資業界からの知見の導入、⑤森林評価手法の確立、⑥人材育成と確保、といった点に大きく整理できる。
まず、「収益性の向上」は、いかにして売上を増やし費用を減らすかで、それぞれの方策には大小様々な取り組みが続けられている。そのベースとして、資産管理・在庫管理として基本情報を整備することや、木材の流通コストを下げるための林道整備のさらなる充実は、「インフラ整備」として最優先課題と考えられる。また、「まとまった規模の森林」が条件となるのは、高性能機械の導入等による費用の削減につながるからであり(ただし、比較的小規模な森林における自伐型林業を否定しているわけではない)、投資資金を外部から調達するには、投資対象の資産規模がまとまっていることも運用効率上望ましい。
では、これらの条件が整った森林であれば、十分な収益を挙げる林業経営が成されているのだろうか?森林経営の実例として、ある期間にこれぐらいの利回りで運用がされてきたという具体的な数字を、筆者は寡聞にして知らない。大規模に森林を保有する上場企業においても、森林経営の実情にかかる情報開示は-CSRの活動報告は多数存在するが-、見られないといって良いだろう。すなわち、森林経営が数値化され、金融や投資の視点から考えられているとは言いがたいのが現状であり、その端的な例は森林資産の評価手法の「遅れ」にも現れているだろう。
さらに、これらの条件が満たされたうえで-あるいは満たされるために-、伐採・搬出・植林の現場(川上)から、森林関連ビジネスを革新し実践していく現場(川中・川下)にいたるまで、人材の確保と育成も急務である。熊崎実筑波大学名誉教授の指摘を引用すれば、「オーストリアでは林業が健全な状況を維持するために必要なことは『インフラ、教育、補助金』の順番と言われるが、日本ではこの順番が逆になっていないか?」ということになる。
以上述べたとおり、日本で森林ファンドを実現するには課題が山積しているが、筆者は、その可能性に希望を持っている。近年、木質バイオマスのエネルギー利用の本格化に伴い、林業そのものの収益性が改めて問われている。また、一昨年頃から、海外の森林ファンドのセールスが国内でも活発化し、同時期の野村證券株式会社による国内森林を活用した証券化への試みも特筆されるべきできごとであった。「儲かる森林」と「儲からない森林」を区分けし管理運用することは、資本の論理抜きには語れず、それを通じて森林が持つ公益性もより明確になるはずである。
「愚公、山を移す」という故事もある。本稿が、森林という自然資源がより有効に活用されることの一助になればと願いつつ、勝手ながら、2017年を「森林ファンド元年」と称する次第である。
関連レポート・コラム
- (リサーチカフェ)森林ファンド元年(上) -動く山-(2017年3月29日)
- (リサーチカフェ)林業のすゝめ(2015年2月19日)