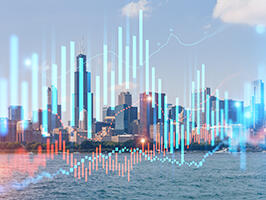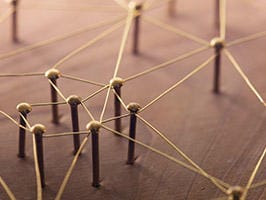理事(研究推進業務担当)
馬場 高志
不動産市場・ショートレポート(8回シリーズ)
アフターコロナでの新しい不動産市場③/賃貸市場(住宅)
首都圏で住まいの地方化・郊外化が進展。賃貸物件も対勤務地利便性の高い物件で稼働率悪化。
投資対象としての賃貸住宅、とりわけ大都市に立地する賃貸マンションは、これまでリスクの小さいアセットタイプと目されてきた。このため同市場には、未曾有のコロナ禍においてさえ、低金利や運用難を背景に国内外の投資資金がこぞって流入し、賃貸マンションに対する投資・取引・開発が活発化している。ただし東京23区では、コロナ禍を機に普及拡大したテレワークを前提に住まい方が大きく変化しており、従来の賃貸マンション投資に対する市場見通しは、変更を余儀なくされるかも知れない。
これまで国内の大都市では、潤沢な雇用を背景に、毎年、各都市の人口の0.1~0.8%に当たる純流入(=転入超過率=(転入者数-転出者数)/人口)が続き、これに伴い、受け皿となる賃貸マンション需要も拡大してきた。しかしコロナ禍は、そうした都市の人口移動、とりわけ東京23区の人口移動を一変させた。東京23区の足元3ヶ年の転入超過率を移動地域別に見ると、対地方(=その他)および対首都圏はいずれも急減し、足元ではその動きが加速している。なおこうした動きは、①雇用や所得の低迷に伴う、不動産コスト(貸家賃料・持家価格)の負担力低下、②テレワークの普及に伴う、住まいの選択基準の変化(対勤務地利便性→テレワーク環境)、の2つの要因による。①は雇用・所得の回復に伴い解消されるが、②は今後さらに多くの企業および就業者へ波及するため、首都圏人口の地方化および郊外化は、引き続き進むと予想される。
こうした人口移動の影響は、賃貸マンション市場の変容としても表れている。すなわち、コロナ禍前に支持を集めていた、<18~30㎡/都心ターミナル駅/駅歩5分以内>などの物件で稼働率が低下し、逆に<30㎡以上/郊外・地方/駅歩5分超>などの物件で稼働率が堅調となっている。さらに既存物件のオーナーは、稼働率を維持するため募集賃料あるいは初期費用を見直し、また新規物件のオーナーは、供給時期の延期や広い居室を増やす等の対応を余儀なくされている。
なおこうした住まい方の変化が、今後<強まるor弱まる><一過性or経常的><解消or残存>等の方向性は、現在、各法人での働き方および各個人の住まい方が模索されている段階であり、判断しにくい状況にある。今後の賃貸マンション市場を見通すためにも、引き続きこうした人口移動の行方が注目される。
関連レポート・コラム
- 不動産市場・ショートレポート(8回シリーズ)
- アフターコロナでの新しい不動産市場①/新型コロナウイルスの影響(2022年2月28日)
- アフターコロナでの新しい不動産市場②/賃貸市場(オフィス)(2022年3月1日)
最近の執筆レポート・コラム