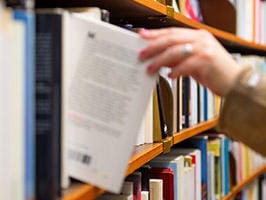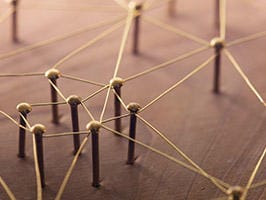私募投資顧問部 上席主任研究員
菊地 暁
社会(S)に広がる財務情報開示の動き
サステナビリティ財務情報開示の動きが加速している。
2015年にTCFDが発足したのち、2021年にはTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)が、そして2024年9月にTISFD(不平等・社会関連財務情報開示タスクフォース)と、矢継ぎ早にサステナビリティ財務情報開示タスクフォースが発足した。これまでは環境(E)を中心に、気候変動と自然資本に関する情報開示の枠組構築が進められてきたが、TISFDはこれらを応用し、社会(S)関連の情報開示の枠組を策定するものである。このTISFDは、企業に対して人権問題や労働環境、多様性・包摂性などに関する財務的リスクと機会の開示を求めている。
社会(S)については、2023年に国土交通省が「「社会的インパクト不動産」の実践ガイダンス~評価と対話のツール~」(以下「ガイダンス」)を公表し、社会課題解決に向けたロジックモデルが示されている。ガイダンスでは、社会課題の重要性・優先順位を「マズローの欲求5段階説」の考え方を用いて階層を整理し、「人権の尊重」を根本的な社会課題として位置づけ、「安全・安心」と並ぶ最も基礎的な階層として位置づけた。これは、そもそも日本国憲法が「基本的人権の尊重」を三大原則のひとつに掲げていることに加え、全ての人が精神的に良好な状態を維持し、ウェルビーイングを実現するためには、その土台としてまず個々の尊厳が守られるべきであるという理念に基づいている。
不動産と人権との関わりは多岐にわたる。不動産の開発段階では、労働環境が十分に整備されているか、外国人技能実習生(労働者)の人権に配慮出来ているか、などが該当する。さらに、建設時に使用されるコンクリート型枠用合板パネルの多くは、南洋材(マレーシア、インドネシア等)を原料としており、原産林における先住民の土地収奪や環境破壊等が問題視され、一部には違法伐採木材が含まれているとNGO等から指摘されている。都市開発では、合法であっても、環境破壊や強制退去などがあると、近隣住民の苦情等により開発が頓挫し、開発による社会的有用性が得られなくなるケースも散見される。地域住民の人権に配慮しつつ、開発者と地域住民との間に軋轢が生じないよう、これまで以上に地域との対話が重要となる。
不動産運用段階では、テナントの従業員が適切な労働環境下にあるか、あるいは、テナントがメーカーや飲食業運営会社だった場合などは、資材調達のサプライチェーンに人権侵害に加担する事項がないか、などの人権デューデリジェンスの視点が必要となってくる。どの程度の人権デューデリジェンスを行うかは、実行可能性を踏まえ、今後議論していく必要がある。また、多様性と包摂性の実現に向けた建築物の整備や設備の設置が進められており、全ての人が施設・サービスを円滑に利用できる状態が望ましい。
TISFDの発足により、社会課題の基礎的な階層と位置づけられた「人権の尊重」について、その実現可能性と透明性が問われることとなる。企業は、改めてマテリアリティ(重要項目)を見直し、投資家とのエンゲージメントを踏まえた人権に関する具体的な取組の推進と、リスク・機会について財務インパクトの測定を進めて行く必要がある。今後のTISFDの動向には注視したほうがよいだろう。
(株式会社不動産経済研究所「不動産経済ファンドレビュー 2025.1.25 No.686」寄稿)